債務整理
【徹底解説】任意整理とブラックリストの関係!いつ登録され何年で消える?
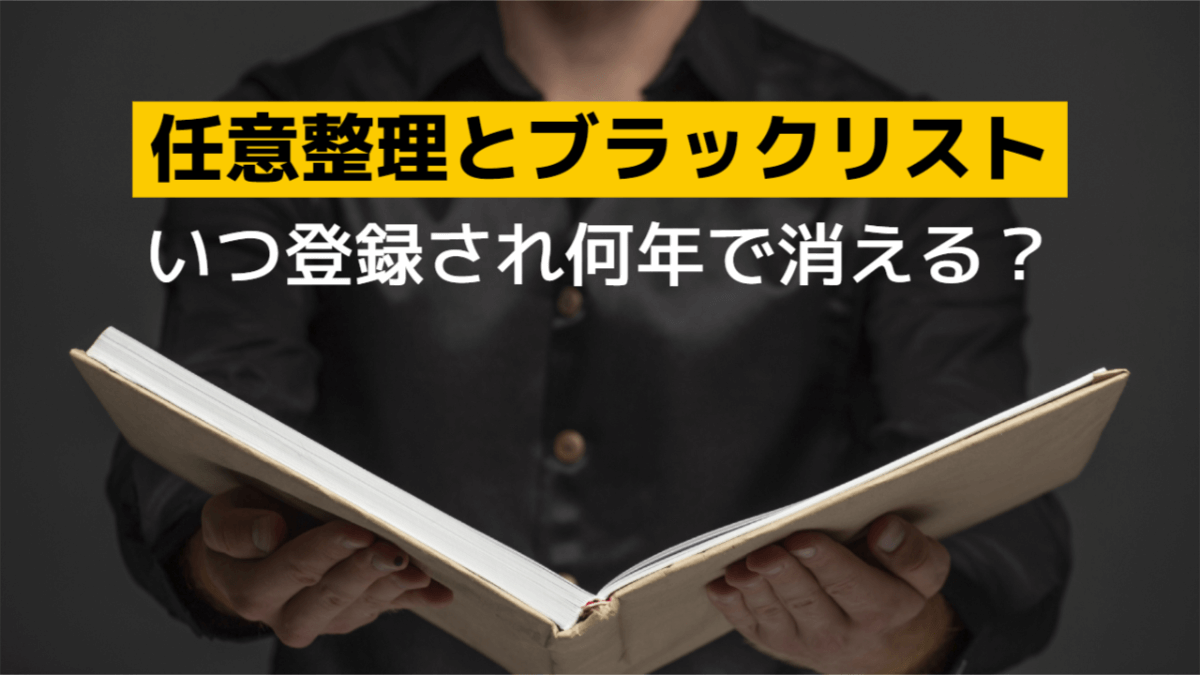
「任意整理されたら、ブラックリストに登録されるの?」
「ブラックリストに登録されたらどんな影響があるの?」
任意整理を検討されている方のなかで、ブラックリストとの関係が気になっている方は多いのではないでしょうか。
実は、任意整理をしても、必ずブラックリストへ登録されるわけではありません。
この記事では、ブラックリストの概要から任意整理との関係を細かく解説しています。
任意整理とブラックリストの関係について理解を深めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.任意整理でブラックリストに登録されるタイミングと期間
任意整理をしたら、必ずブラックリストに登録されるのでしょうか。
実は、「ブラックリストに登録されるケース」と「ブラックリストに登録されないケース」が存在します。
任意整理の流れを確認したうえで、それぞれのケースを見ていきましょう。
1-1.まずは任意整理の流れをおさらい
任意整理は、大まかに以下の流れで進みます。
1.まずは自身の債務状況を整理し、自力での返済は困難であることを確認する
2.専門家に相談のもと、「引き直し計算」をおこなう
3.もし払い過ぎたお金(過払い金)があったら、負債からその分のお金を減らす
4.引き直し計算後も負債が残った場合は、「今後発生する予定の利息をゼロにして、残っている負債だけを分割払いで支払っていく」ことを最終目標として、債権者と交渉する
任意整理をした当事者は、以上のような流れによって、任意整理前と比較して返済の負担を減らせることとなります。
1-2.任意整理によってブラックリストへ登録されるケース
任意整理後にブラックリストへ登録されるのは、「任意整理による引き直し計算後もなお負債が残った場合」です。
任意整理後も負債が残れば、「任意整理をした」という事実が事故情報として信用情報に登録されることとなります。
さらに、信用情報機関によっては「任意整理によって債権者と交渉をおこなった」という事実だけでも事故情報として扱われることもあるので、注意が必要です。
1-2-1.任意整理後ブラックリストに登録されるタイミング
任意整理後ブラックリストに登録されるタイミングは、「司法書士や弁護士などの専門家に任意整理の手続きを依頼し、債権者へ受任通知が送られたタイミング」です。
専門家に依頼し任意整理の手続きが開始されると、債権者に受任通知が送られその時点で信用情報に事故情報が登録されます。
受任通知とは、「債権者に対して債務者が任意整理を始めることを伝えるための通知」です。
債権者は、受任通知を受け取った段階で債務者への返済請求や催促を停止する必要があり、返済自体もストップされます。
1-2-2.任意整理後ブラックリストから消えるタイミング
ブラックリストから消えるタイミングは、任意整理によって借金を完済してから5年程度です。
一般的な借金返済の期間を含めると、任意整理の手続を開始してから7年~10年程度となります。
「程度」としている理由は、信用情報機関によって情報を保持する期間や更新するタイミングが異なるためです。
1-3.任意整理後にブラックリストへ登録されないケース
任意整理をしても、「引き直し計算によって計算された過払い金が負債を超えていた場合」であれば、ブラックリストへは登録されません。
ただし、任意整理をした時点で事故情報が登録されるため、引き直し計算が終了するまでは一時的にブラックリストへ登録されることにはなるため注意が必要です。
また、過去に完済した負債に対して過払い金請求だけをおこなった場合も、ブラックリストへは登録されません。
なお「完済した」とは、「同じ債権者に対する負債すべてを返済した」ことを指します。
そのため、たとえば同じ会社からのキャッシングはすべて返済していても、ショッピングによる負債が残っているのであれば、完済したことにはなりません。
以上のような状態で引き直し計算をした結果、ショッピングによる負債をすべて返済できないのであれば、ブラックリストに登録されることとなりますので注意してください。
2.そもそもブラックリストとは?
ここまで「任意整理とブラックリストの関係」について解説をしてきましたが、そもそもブラックリストとはなんなのでしょうか。
ここからは、「ブラックリスト」について詳しく解説をしていきます。
2-1.ブラックリストとは信用情報へ事故情報が登録された状態
正確にいうと、ブラックリストというものは存在しません。
任意整理をしたときに個人の信用情報へ「事故情報」が登録されますが、この状態を一般的に「ブラックリスト入りした」と表現するため、ブラックリストという言葉が広く知られています。
2-2.信用情報を扱う3つの信用情報機関と信用情報機関に登録される情報
「信用情報」とは、借入やクレジットカードの利用状況・ローンに関する情報など「個人の支払いに関する情報」のことです。
そして、日本国内で信用情報を取り扱っている主要機関は以下の3つで、それぞれの機関で取り扱っている情報が異なります。
| 信用情報機関 | 取り扱っている主要な情報 |
|---|---|
| JICC(日本信用情報機関) | 消費者金融をはじめとした貸付業者との取引履歴 |
| CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカードでの支払い履歴 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行や地方銀行などの金融機関との取引履歴 |
個人が金融機関から借入を希望するとき、金融機関は信用情報機関に登録されている信用情報を確認し、その人へお金を貸しても問題がないか審査するという流れです。
信用情報機関へ登録される情報を細かくご紹介していきます。
2-2-1.申し込みに関する情報
新規でローン・クレジットカードなどを申し込んだとき、以下のような申し込みに関する情報が登録されます。
- 氏名
- 生年月日
- 郵便番号
- 電話番号
- 申込日
信用情報機関によって差はありますが、6ヶ月〜1年間は情報が登録されます。
2-2-2.契約に関する情報
借入・ローンなどの契約に関する情報として登録されるのは、以下のような内容です。
- 契約した日
- 商品名
- 支払回数
- 契約金額
これらの情報は、最長で5年間登録されます。
2-2-3.借入に関する情報
借入・キャッシングなどでお金を借りたときは、以下の情報が登録されます。
- 商品名
- 借入日
- 借入金額
- 返済予定日
借入に関する情報も、契約に関する情報と同じく最長で5年間は登録されます。
2-2-4.支払いに関する情報
借りたお金の返済や返済日などの情報については、以下の情報が登録されます。
- 入金日
- 借入残高
- 完済日
- 延滞日
支払いに関する情報も、最長で5年間は登録されます。
2-2-5.事故情報に関する情報(ブラックリスト)
「事故情報」とは、任意整理をはじめとした債務整理をしたことや借金の返済が滞ったなど、個人の金銭的な信頼に関わる情報を指しています。
自己情報に登録されるタイミングは、信用情報機関によって以下のような差があります。
| 信用情報機関 | ブラックリストへ登録されるその他の条件 |
|---|---|
| JICC(日本信用情報機関) | ・任意整理を含む債務整理がおこなわれたとき・返済を3ヶ月以上延滞したとき・保証会社によって代位弁済されたとき |
| CIC(株式会社シー・アイ・シー) | ・返済から61日以上または3ヶ月以上延滞したとき・保証会社によって代位弁済されたとき |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | ・加盟している金融機関から報告があったとき・保証会社によって代位弁済されたとき |
事故情報が登録される(ブラックリストへ登録される)と、信用情報機関同士で情報が共有されます。
そのため、いずれかの信用情報機関で事故情報が登録された段階で、新しくクレジットカードを作ったり借入を受けたりすることはできなくなるというわけです。
2-3.自身の信用情報を調べる方法
自身の信用情報を確認し、ブラックリストに入っているか否かを確認するためには、各信用情報機関へ情報開示をおこなう必要があります。
各信用情報機関への情報開示方法は、以下のとおりです。
| 信用情報機関 | 情報開示の方法 |
|---|---|
| JICC(日本信用情報機関) | アプリ・郵送・窓口 |
| CIC(株式会社シー・アイ・シー) | インターネット・郵送・窓口 |
| KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 郵送 |
詳しくは、それぞれの信用情報機関のサイトを確認してください。
2-3-1.金融機関には情報が残り続ける可能性がある
1つ注意すべきなのが、信用情報機関上では情報が消えたとしても、任意整理をした金融機関では「過去に任意整理をされた債権者」として情報が残り続ける可能性があります。(いわゆる「社内ブラック」)
金融機関に情報が残り続けている場合は、企業グループ内で共有され、グループ内の会社から新規で借入をするのは困難でしょう。
また、企業で情報を残しグループ内で共有しているか否かは、金融機関によって異なります。
2-4.ブラックリストに登録されても家族に影響はない
ブラックリストに登録された場合、影響が出るのは登録された当事者だけです。
そのため、家族や恋人には特に影響がありません。
ブラックリストに登録されれば、当事者は新規の借入を受けられなかったり賃貸契約をできなかったりする可能性があるものの、家族や恋人へ直接的なペナルティは課されません。
ただし、当事者の保証人に家族や恋人がなっている場合をはじめケースバイケースで影響が及ぶこともあるため、家族や恋人への影響が気になる方は専門家に確認するのがおすすめです。
2-5.ブラックリストに登録されても周囲には知られない
ブラックリストに登録されても、周囲にその事実を知られることはありません。
事故情報は、あくまで信用情報のみに登録されるだけであり、戸籍やパスポートなどに登録されるわけではないためです。
ブラックリストに登録された情報を確認できるのは、当事者と信用情報機関に加盟している金融機関のみです。
また、保証人がついている借金を除外して任意整理を進めることも可能なので、保証人がついている借金を任意整理したことで「任意整理がおこなわれた」という事実を保証人に知られるリスクを軽減できます。
3.任意整理後のブラックリスト登録中にできない5つのこと
任意整理後のブラックリスト登録中にできないこととして、主に以下の5つがあります。
- 新規の借入ができなくなる
- 賃貸契約をできない可能性がある
- クレジットカードを使えない・新規で作れない
- 保証人になれない
- 買い物で分割払いができなくなる
それぞれ解説していきます。
3-1.新規の借入ができなくなる
ブラックリストに登録された場合、新規の借入はできません。
任意整理によってブラックリストに登録されている状態では、金融機関の審査に通らないためです。
また、「ブラックリストに入っていてもお金を貸せます」と営業をしてくる金融機関がありますが、違法な金融機関である可能性が高いため注意してください。
任意整理と借入については、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
任意整理中に借入できる?ばれるとまずい?リスクや対処法を解説
3-2.賃貸契約をできない可能性がある
ブラックリストに登録されている状態では、賃貸契約をできない可能性があります。
賃貸契約をおこなうとき、契約者に対して保証会社と契約することを義務付けられることがあり、信用情報機関の情報を使って保証の審査をする保証会社であれば、保証をしてもらえなくなってもらえるためです。
ただし、保証会社による保証は必ず求められるものではないため、事前に不動産会社に相談したうえで賃貸契約を進めるようにしてください。
3-3.クレジットカードを使えない・新規で作れない
ブラックリストへの登録が終わるまでの5年間は、クレジットカードを使えないうえに新規で作ることもできません。
クレジットカードによる決済は、一時的にクレジットカード会社に立て替えてもらっているいわば「借金」であるためです。
なお、任意整理の申請時に使っていたクレジットカードが使えなくなるタイミングは、クレジットカード会社によって異なります。
任意整理とクレジットカードについては、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
任意整理中クレジットカードは作れる?和解後はどう?作れたケースや注意点も解説
3-4.保証人になれない
他者の借金保証人となることはもちろん、以下のような保証人になることもできません。
- 住宅ローン
- 子どもの奨学金
- 未成年によるクレジットカードの作成
そのため、配偶者や親族などの他の人へ、保証人になってくれないかを依頼する必要があります。
3-5.スマートフォンの分割払いができなくなる
スマートフォンを分割払いによって購入される方が多いですが、ブラックリストに登録されるとその分割払いができなくなります。
「分割払い=ローン」として同じ扱いとなり、スマートフォンの分割払い時は信用情報を確認されるためです。
そのため、スマートフォンを購入するときは、格安スマホを購入するか、分割ではなく一括で購入する必要があります。
関連記事:任意整理中にスマホ(携帯)分割払いは可能?審査に通った事例も解説
4.任意整理後にブラックリストへ登録されてもできること3選
ブラックリストへ登録されたとしても、以下の3つは変わらずにおこなえます。
- 生命保険へ加入する
- 不動産賃貸借の連帯保証人になる
- 新規で銀行口座を開設する
1つずつ解説していきます。
4-1.生命保険へ加入する
ブラックリストへ登録されていても、生命保険への加入は可能です。
生命保険会社は金融機関ではなく、信用情報機関にも登録されていないので、生命保険の審査で任意整理の状況は確認されないためです。
4-2.不動産賃貸借の連帯保証人になる
たとえば子どもが賃貸契約をするときに、保証会社との契約が不要な賃貸契約であれば連帯保証人となれます。
保証会社との契約が不要な賃貸契約であれば、連帯保証人の信用情報を確認されることがないためです。
4-3.新規で銀行口座を開設する
銀行口座の新規開設は、ブラックリストへの登録の有無に関わらずにおこなえます。
ただし、ブラックリストに登録されていればクレジット機能付きのキャッシュカードは利用できません。
5.ブラックリストからの削除後にできるようになること3選
ブラックリストからの削除後は、以下の3つができるようになります。
- クレジットカードを作成する
- 住宅ローンを組む
- 自動車ローンを組む
5-1.クレジットカードを作成する
ブラックリストから情報が消された場合、クレジットカードを作れるようになります。
ただし、任意整理をおこなったクレジットカード会社では審査に落ちる可能性が高いため、他のクレジットカード会社にてカードを作成されるのがおすすめです。
5-2.住宅ローンを組む
ブラックリストから情報が消えたあとは、住宅ローンを組めるようになります。
住宅ローンの審査時に注意すべきなのが、信用情報以外にも確認されるポイントがあるという点です。
ブラックリストへの登録が消えてからも住宅ローンの審査に落ちたときは、「自身の就労状況」や「頭金の不足額」などを確認してください。
関連記事:債務整理したら住宅ローンはどうなる?家を残して債務整理する方法とは?
5-3.自動車ローンを組む
ブラックリストからの登録削除後は、住宅ローンと同様に自動車ローンを組めるようになります。
ただし、購入を考えている車種次第では多額の資金が必要となるので、自身の資金と照らし合わせながらよく考えるようにしましょう。
任意整理の完済後については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
任意整理完済後すぐにカードやローンは申し込める?完済後の注意点も解説
6.任意整理とブラックリストに関するよくある質問
最後に、任意整理とブラックリストについてよくある質問へ答えていきます。
6-1.Q.任意整理をしたら必ずブラックリストに登録される?
任意整理をしても、必ずブラックリストへ登録されるわけではありません。
任意整理による引き直し計算によって負債が完済された場合は、ブラックリストへは一時的な登録のみとなります。
6-2.Q.過払い金請求はブラックリストに登録される?
過払い金請求をおこなったタイミングによって変わります。
完済後の過払い金請求は、ブラックリストへ登録されることはありません。
任意整理時の引き直し計算によって過払い金請求をする場合には、以下の2通りに分かれます。
- 引き直し計算による過払い金請求によって負債が完済される場合は、ブラックリストへは一時的な登録のみとなる
- 引き直し計算による過払い金請求をおこなってもなお負債が残る場合は、ブラックリストへ登録され、完済後も5年間はブラックリストから削除されない
6-3.Q.任意整理以外の債務整理をしてもブラックリストに登録される?
任意整理以外の債務整理(自己破産や個人再生)をおこなっても、基本的にブラックリストへは登録されます。
債務整理をおこなえば負債を軽くできる一方、ブラックリストへの登録は避けられません。
6-4.Q.任意整理によるブラックリストから消えるのはいつから5年?
任意整理によるブラックリストから消えるのは、任意整理後の完済から約5年です。
ただ、なかには任意整理の和解から5年の場合もあります。
自身がブラックリストに載っているかどうか気になる方は、各信用情報機関へ情報開示をおこなうようにしてください。
7.まとめ
いかがでしょうか。
任意整理によってブラックリストに登録されるかされないかは、引き直し計算後の負債残額で決まります。
また、任意整理によってブラックリストに登録されたとしても、任意整理前よりも負債を減らせるうえに、完済から5年程度経過すれば情報が消えます。
そのため、ブラックリストに登録されることを恐れて任意整理をしないほうがデメリットは大きいです。
返済を滞納してもブラックリストに登録されてしまうため、任意整理を検討されている方は早めに専門家へ相談されるのがおすすめです。
福岡市博多区にある佐藤司法書士事務所では、設立当初から債務整理に注力しており、15年以上の豊富な経験と実績があります。
加えて、初回相談・着手金・減額成功報酬0円で承っておりますので、金銭面や債務整理にお困りの方もお気軽にご相談ください。
「任意整理中だけど借入をしたい」
「任意整理中で借入ができない場合の対処法を知りたい」
「任意整理中の金銭面における問題を適切に解決したい」
このようにお悩みの方は、お気軽に佐藤司法書士事務所へご相談ください。
コラム監修者
- 佐藤司法書士事務所 佐藤 直幸
-
 福岡市で債務整理業務15年以上で経験豊富な司法書士
福岡市で債務整理業務15年以上で経験豊富な司法書士
借金の問題は「早く解決したほうがいい」ということに尽きます。
長く放置して解決できなくなる前にご相談ください。
相談しにくいことではあると思いますが、敷居を低くしてお待ちしていますので
遠慮なくご連絡いただけると幸いです。
誠心誠意対応させていただきます。早めにご相談ください。

